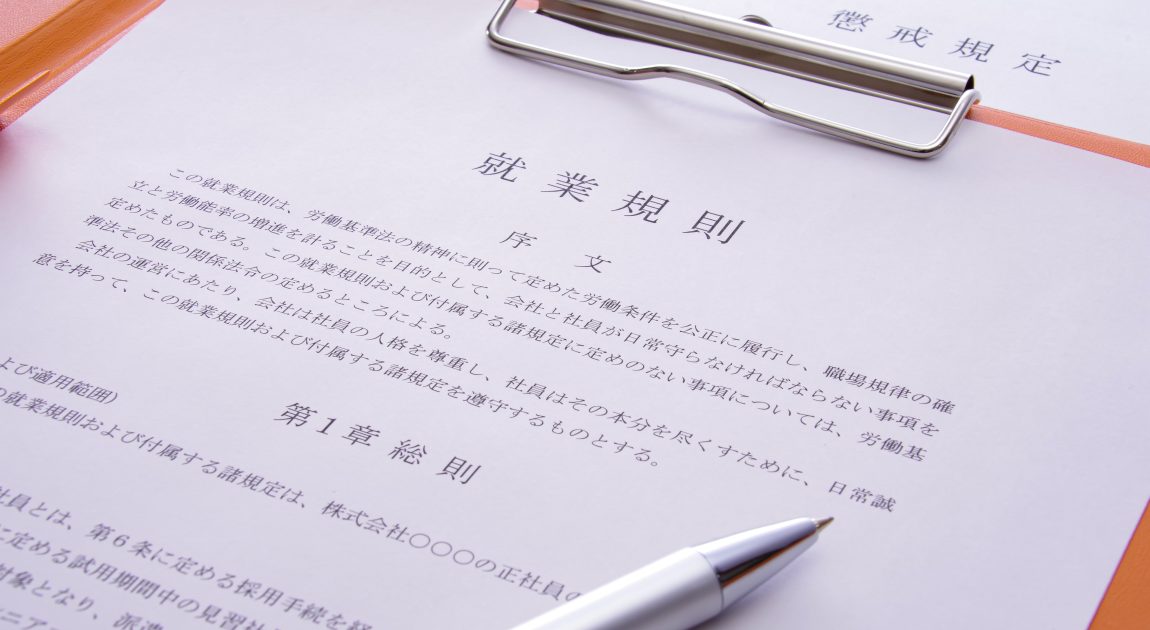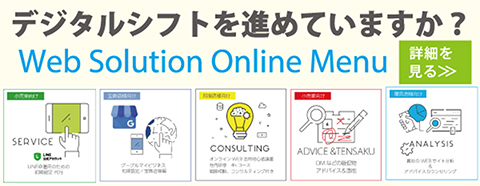こんにちは。
PR現代の佐藤です。
11月に入りました。
秋本番ですが、徐々に寒くなってきました。
とはいえ寒暖差も激しいので、とにかく体調には注意ですね。
紅葉も見に行きたいけれど熊出没のニュースを見ると躊躇していまいます。
今回は会社の法律「就業規則」についてです。
皆さんの会社ではしっかりと整備されていますか?
「就業規則」が経営を守る
―法律改正の波に置き去りにされないために―
多くの小売店では「うちは家族のような職場だから」「社員数が少ないから」といった理由で、就業規則を作っていなかったり、昔に作ったまま見直していないというケースが少なくありません。
しかし、労働環境をめぐる法律はこの数年で大きく変化しています。働き方改革関連法をはじめ、育児介護休業法の改正、パート・アルバイトへの均等待遇、労働条件の明示義務化、ハラスメント防止措置義務など、中小企業にも直接関係する内容が次々に施行されています。
「昔のままの就業規則」や「そもそも就業規則がない」状態は、知らず知らずのうちに法律違反になっている場合もあります。
いざトラブルが起きたとき、会社を守る「盾」になってくれるのが、実はこの就業規則なのです。
■ 就業規則は“会社のルールブック”
就業規則とは、会社と従業員の双方にとっての「ルールブック」です。
労働時間、休日、給与、休暇、退職・解雇などの基本的な取り決めを定めることで、働く上での基準を明確にします。
法律上も、常時10人以上の従業員を使用する事業場には届出義務がありますが、10人未満であっても作成しておくことを強くおすすめします。
なぜなら、トラブルの多くは「言った・言わない」「そんなルールは知らなかった」という認識のズレから起こるためです。
就業規則があれば、ルールを会社と社員の両方が共有でき、感情的な衝突を防ぐことができます。
■ トラブルから会社を守る“法的な盾”
例えば、無断欠勤やハラスメント、勤務態度の不良などのトラブルが起きた場合、就業規則に懲戒や解雇の根拠が定められていないと、会社は法的に不利な立場になります。
一方で、きちんとした就業規則があれば、客観的なルールに基づいて対応できるため、後々のトラブルを防げます。
また、労働基準監督署の調査や助成金申請の際にも、最新の就業規則が整備されていることは重要です。
近年は、電子申請やマイナンバー連携など、デジタル化への対応も進んでいます。
紙のまま古い規則を放置しておくのではなく、クラウドで管理しやすい形に整備しておくことも、これからの時代に求められる姿です。
■ 社員との信頼関係づくりにも役立つ
就業規則は「社員を縛るためのルール」ではなく、「社員を守るルール」でもあります。
たとえば、休暇制度やハラスメント防止、育児・介護への配慮といった項目をしっかり明文化することで、従業員が安心して働ける環境を整えられます。
結果として、離職防止や採用の魅力アップにもつながります。
会社の考え方や方針を明文化することは、経営理念の共有にも通じます。
「うちの会社はこういう考え方で働く人を大切にしている」というメッセージを、就業規則という形で伝えることができるのです。
■ 法改正への対応が“信頼される会社”の条件
ここ数年の法改正はスピードが速く、内容も複雑です。
・2023年:育児介護休業法の改正(男性育休の分割取得など)
・2024年:労働条件明示の電子化義務化
・2025年:マイナ保険証完全移行、労務手続きのオンライン化推進
これらはすべて、就業規則の見直しが必要になるタイミングです。
「前に作ったから大丈夫」と安心していると、気づかないうちに法違反や不備が発生していることもあります。
行政の指導や助成金申請の際に不備を指摘されるケースも少なくありません。
■ 最後に:就業規則は「経営のリスクヘッジ」
経営者の多くは、販売や仕入れ、集客には敏感でも、「人」に関するリスク管理は後回しになりがちです。
しかし、トラブル対応や退職交渉に時間を取られることは、経営にとって大きな損失です。
就業規則を整備しておくことは、“万が一”に備える経営の保険ともいえます。
そして、就業規則は一度作って終わりではなく、定期的な見直しが大切です。
法改正や働き方の変化に合わせて更新し、現場に合った形にしていくことで、会社の信頼性と安定経営につながります。
まとめ
- 小さな会社こそ「ルールの明文化」でトラブルを防ぐ
- 就業規則は社員を守り、会社を守る“経営の盾”
- 法改正に合わせて見直すことが、信頼される会社の条件