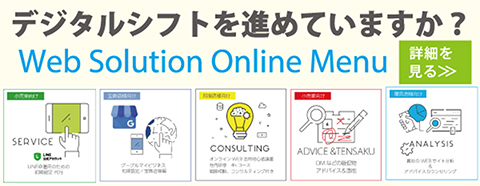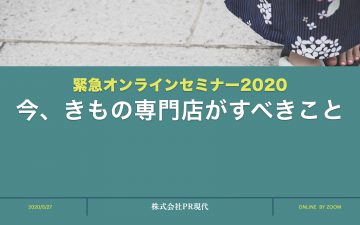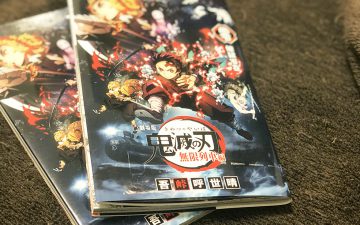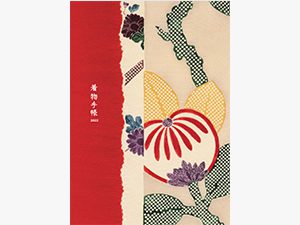これまでの当たり前が通用しないユーザーと向き合う
昨年末あたりから顕著になってきたのが、ユーザーの意識・価値観の変化です。例えば七五三のお客様です。通常七五三といえば、着物を用意して神社にお参りに行くというのが一般的な認識です。七五三はご存じのとおり、住んでいる土地の氏神様がいらっしゃる神社へお参りし、子供の健やかな成長や長生きを願ったのです。昔は、生まれた子が大人になること自体が当たり前でなかったのですね。つまり、氏神様にお参りに行くことが七五三の本質であり、着物を着ることや写真を撮ることはある意味後付けです。しかし、昨年の11月、あちこちで聞かれたのが、お参りに行かない家族の多さです。着物を着て家族で写真を撮ることが七五三のメインイベントになり、お参りはしないというわけです。おそらく、お参りすることが形骸化し、手軽に家族のイベントとして記念になるアクションだけを行うものに変質してしまったと言えます。まだまだ少数ではありますが成人式に参加しないお嬢さんも増えてきています。
それだけではありません。先日関東の着物専門店の経営者から伺ったのが、「振袖」という言葉を知らない親御さんが現れたことです。「浴衣はありませんか?」と来店した際に質問をしてきたそうですが、このお客様は振袖のことを浴衣と呼んでいたのだそうです。「成人式に着る浴衣」と。成人式の着物でもなく、浴衣と言ったとのことで、びっくりしたとおっしゃっていました。これを裏付けるものとして、検索キーワードで「成人式 着物」や「成人式の着物」というワードの使用率が高まっているといったことがあります。
そもそも論としての情報発信をより積極的に行なっていく必要性
私たちが思っている以上に、世代が変わり、一般常識と言われるものの内容も変わってきているということだと思います。それゆえに「成人式に着る着物は、振袖という名前で、袖が長く・・・」「七五三とは本来・・・」といった情報をユーザーに発信し、啓蒙していくことから始めていく必要があります。考えなくてもスマホで検索すれば、なんでも答えが出てくる、AIがなんでも教えてくれる時代だからこそ、あらゆることを頭に記憶としてとどめておく必要がなくなってきてしまったことも関係があるかもしれません。私自身、カーナビを使うようになってから道を覚えようという意識が圧倒的になくなってしまいました。いずれにしても、今私たちが日頃ブログやニュースなどで発信している情報は応用編であることが多く、七五三や振袖というものがどんなものかをわかっている前提でコンテンツ化しています。
いったん立ち止まって、来店されるお客様から発せられる質問や要望、疑問をしっかりと伺い、記録に残しておく必要があります。
一度伝えればそれでOKでなく、繰り返し伝えていく
最近、AIチャットボットをウェブサイトに実装したお店からいただいた情報を読んで感じるのは、伝わっていると思っていたことの多くが伝わっていないことです。AIチャットボットというのは、ウェブサイトに設置してあるチャットの最新版で、ウェブサイトに記載されている情報を学び、ユーザーが質問をするとその質問に対する答えをAIが考え、人間のように返答するツールです。このツールでやりとりされた情報はデータベース化されるのですが、ユーザーから投げかけられる質問の多くは、ウェブサイトに詳細に記載されているものばかりです。それも分かりやすく提示してあるレベルのもので、ほぼ基礎的な内容です。このことから、ウェブサイトへの情報の掲載の仕方を見直すといった改善も必要ですが、一度伝えたからといって多くユーザーには伝わっていないものと考え、繰り返し工夫をしながら情報を発信していくことが大切です。
お客様の意識、私たちの日常、社会、デジタル技術など、変化するスピードがどんどん早くなっています。お客様の声や態度、検索キーワードなどから見える潜在的な検索意図に目を光らせ、常に情報をインプット、そしてアップデートしていく習慣を身につけていきましょう。